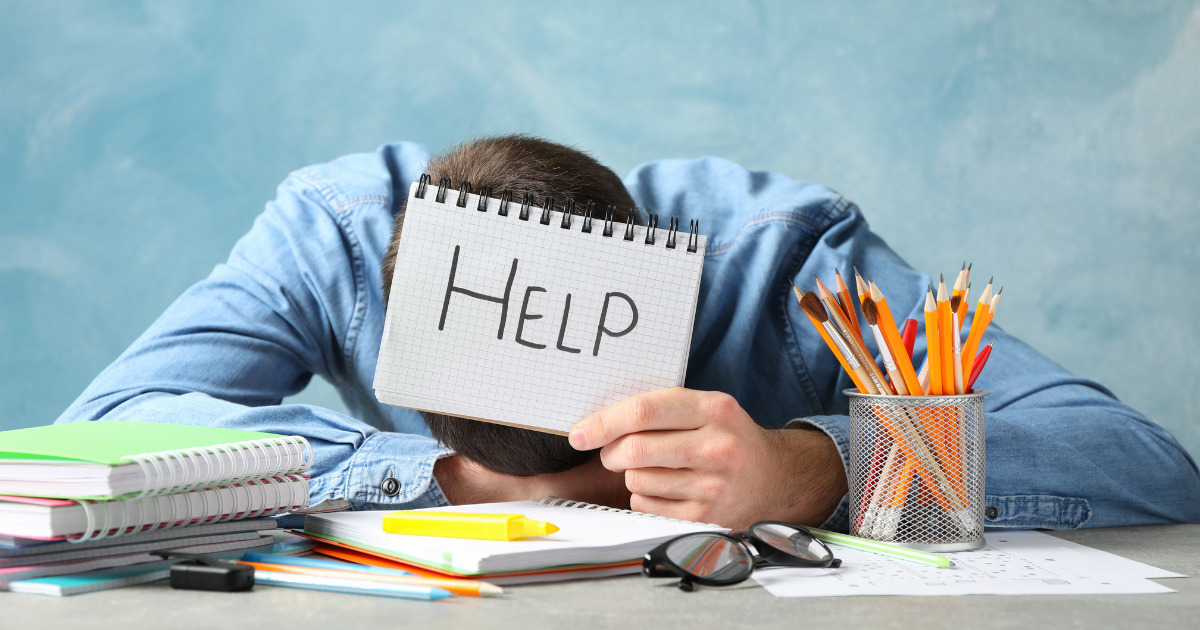こんにちは、Kdanライターの津山です。今、日本では少子高齢化により働き手が減り、年々パート社員が増えています。ですがパート社員を雇う皆さんの中には、正社員じゃないからいいだろうと考え雇用契約書を作成していない方も多いのではないでしょうか?
今回は、パート社員の雇用を常態的に行う事業者の皆様に向けて、パート社員の雇用契約書の重要性、雇用契約書に記載すべき内容、そして雇用契約書を簡単に作成・管理する方法まで、契約書に精通したKdanのノウハウをもとにまとめてお伝えします!
柔軟性が高く採用しやすいパート社員ですが、雇用契約書がないと事業者が痛い目に合うかもしれません。この記事で雇用契約書の重要性をしっかり理解して、雇用トラブルのリスクを減らしましょう!
ここが気になる!パート社員の雇用契約書に記載すべき事項
パート社員の雇用契約書には正社員向けの内容に加えて記載するポイントがあります。ここではパート社員だからこそ気をつけたい雇用契約書の記載内容をまとめてお伝えします!
まず雇用契約書を作成する際は必ず以下の内容を記載します。これらは労働条件通知書で記載が必須となっている項目です。
雇用契約書に記載すべき主な事項
①労働契約の期間(3年以内)
労働条件通知書には、雇用契約の期間を明示する必要があります。通常、契約の期間は3年以内と指定されますが、必要に応じて契約期間の詳細を具体的に記載します。期間の開始日と終了日を明確に記載しましょう。
②就業場所
就業場所については、具体的な住所や場所を詳細に記載します。これには、オフィス、工場、店舗、またはリモートワークの場所などが含まれます。住所や場所が変更される場合には、変更内容を通知しなければなりません。
③業務内容
従業員の業務内容については、具体的で詳細な情報を提供します。これには、役割、責務、プロジェクト、タスク、および期待される業績などが含まれます。業務内容の明示は、従業員の役割と責任を理解しやすくし、誤解や紛争を防ぎます。
④始業・終業時刻
始業と終業の時刻については、具体的な時刻や労働日の長さを示します。これには、通常の労働時間や週の労働日数が含まれます。残業や休日労働に関する規則も含めるべきです。
⑤休憩時間
休憩時間については、労働者が取るべき休憩の長さとタイミングを詳細に記載します。これには昼食休憩、休憩の頻度、および休憩施設の利用方法などが含まれます。これにより、労働者が法的に要求される休憩を取りやすくなります。
⑥休日・休暇
労働条件通知書には、労働者が受けられる休日と休暇に関する詳細な情報を含めます。これには法定の休日、有給休暇、病気休暇、年次有給休暇などが含まれます。休暇の取得条件や手続きについても記載しましょう。
⑦賃金の計算方法
賃金の計算方法については、給与の額、支払いサイクル(月給、週給、時給など)、賞与、手当などを明示します。賃金の支払い方法や給与の変更に関する規則も含めるべきです。労働者が給与の計算方法を理解しやすくし、報酬に関する透明性を確保します。
⑧退職に関する事項
労働条件通知書には、従業員が退職する場合の手続きや条件に関する情報を含めます。これには退職通知期間、給与の支払い、未使用の有給休暇に関する規定、离職手続きなどが含まれます。従業員が退職時に適切な情報を持ち、スムーズな過程を確保するのに役立ちます。
パートタイム労働法も意識する
さらにパート社員の場合、パートタイム労働法で使用者側が以下4つの項目をパート社員に通知する義務があります。こちらも雇用契約書に一緒に記載するようにしましょう。
①昇給の有無
昇給の有無について明示し、もし昇給がある場合、昇給の基準や頻度を具体的に説明します。たとえば、昇給の基準が業績評価に基づく場合、その評価方法とタイミングについて説明します。
②退職手当の有無
退職手当が提供される場合、その条件や支払い方法について具体的に説明します。退職手当の支払い条件や金額、取得のための要件などを示します。
③賞与の有無
賞与が支給される場合、賞与の有無、支給サイクル(年次、半期ごと)、支給の基準(業績、評価など)について明確に説明します。賞与の金額や計算方法も含め、従業員に透明性を提供します。
④相談窓口
相談窓口については、従業員が問題や疑義を提起できる場所や担当者の情報を提供します。これには上司や人事担当者、雇用主への連絡方法やアドレス、電話番号などが含まれます。また、労働条件通知書には、従業員が問題を報告しやすい方法や手順についても言及することが重要です。
また、パート社員であっても、雇用契約書は労働条件を変更したときはもちろん、そのままの条件で契約更新する場合にも、契約書の再締結が必要です。
多くのパート社員を採用している企業は、気が付いたら更新を忘れていた!ということがないように、管理面にも注意しましょう。
雇用契約書を作成する際に知っておくべきこと
雇用契約とは?
まず最初に雇用契約について簡単におさらいします。雇用契約は「労働者が使用者の労働に従事し、使用者がその労働に対して報酬を支払うことを約束する」という民法623条で定義された内容のことを指します。
実は雇用契約は、双方が同意した場合、口約束でも契約が成立します。つまり雇用契約書を作成しなくても法律上の罰則はありません。
なぜ書類を作成する必要があるのか?
雇用契約書をなぜ作る必要があるのでしょうか?それは労働者と使用者の間の労働契約の内容を、誰の目から見ても明確にするためです。もし雇用契約書がなければ、労働者と使用者の間でトラブルがあってもどちらが正しいのか判断できなくなります。
雇用契約書と労働条件通知書との違いは?
事業主の方の中には、労働条件通知書があればいいのでは?と考える方もいるでしょう。ですが結論から言うと雇用契約書は必要です。ここでは労働条件通知書との違いを簡単に説明します。
まず労働条件通知書とは「使用者が労働者を採用する際に通知しなければならない事項を記載した書面」です。こちらは労働基準法第15条で交付が義務化されており、違反したら使用者に30万円以下の罰金が課されます。
では労働条件通知書と雇用契約書の違いは何か?それは労働条件通知書が「使用者から労働者への一方的な通知」であるのに対し、雇用契約書は「双方が署名・捺印する」点です。
雇用契約書があれば労働者から「受け取っていないから知らない」と言われるトラブルの防止に繋がります。
雇用契約書は何で作成したらいいの?
雇用契約書は紙または電子での作成が可能です。従来は紙で作成していた事業者が多かったのですが、2019年4月から労働条件通知書の電子化が認められるようになりました。それに伴い今後は雇用契約書でも電子化が進むと考えています。
労働条件通知書をはじめ、人事関連の書類についての電子化事情を詳しく知りたい方はこちらのブログも参考にしてください。
パートの雇用契約書がない使用者側のデメリット3つ
パート社員は短期間だからリスクが高くないと安易に考え、雇用契約書を作成しない、あるいは内容を精査しない使用者もいます。ですがそれは使用者にとって大きなデメリットがあります。ここでは3つお伝えします。
① 会社に対する信頼が下がる
雇用契約書がなければ、労務管理がおろそかになっているとみなされ、従業員の信頼が下がります。そうなると離職率が高まったり、あるいはネットで信頼を下げるような噂を流されたりするリスクが高まります。
② 勤務時間や転勤など労働条件が不明確になる
勤務時間や業務範囲も正社員と異なることが多いのがパート社員です。就業規則だけでなく雇用契約書で明示しなければ、予期せぬ訴訟リスクにつながります。
過去に、転勤ルールについて「就業規則に記載していた」ことを理由に雇用契約書に記載しなかった使用者が、転勤を拒否したパート社員社員を解雇したところ、裁判で敗訴した事例もあります。
③ 残業代や手当の範囲が不明確になる
残業代や手当に関しても、雇用契約書に記載がないと予期せぬ追加支払いが生じます。過去にパート社員の給与にみなし残業費用を含めていた会社が、雇用契約書にその旨の明記がなかった、という理由で残業代の追加支払いを命じられた裁判事例もあります。
トラブル回避のためにも、雇用契約書にきちんと労働条件や給与の支払い方法などを明記し、パート社員の理解と合意を得ることが大切です。
パート社員の雇用契約書の作成を簡単に行う方法
では最後に、今からパート社員の雇用契約書を作成したい、あるいはもっと効率的に管理したいと考える事業者の方に向け、雇用契約書を簡単に作成・管理できる方法をお伝えします!それがテンプレートの利用と電子化です。
新規作成の場合、一から作る時間のない事業者の方も多いと思います。そんな時はテンプレートを活用すればすぐに明日からでも雇用契約書が発行できます。
例えば、Kdanが提供するPDF Readerのページでは、先ほどの「パート社員の雇用契約書に記載すべき事項」で紹介した内容がほとんど網羅されたフォーマットを無料で提供しています。
また雇用契約書の更新管理や手続きが煩雑になっている事業者の方には、雇用契約書自体を電子化してしまうことが最も有効です。
電子化と言ってもただ雇用契約書をスキャンするのではなく、Kdanが提供する電子サインサービス「DottedSign(ドットサイン)のように、契約書のサインからオンラインで全て締結できるサービスを活用するのがオススメです。
▶︎モバイルでも、PCでもいつでも契約締結 DottedSign(ドットサイン)
アルバイト社員に向けた入社手続きに関するアンケート調査では、約90%の人が入社手続きをスマホで完結したいと回答しています。これはおそらくパート社員でも同様の傾向があると考えられます!
雇用契約書のサインから管理まですべて電子化することで、事業者側の管理効率が改善するだけでなく、パート社員側の利便性も向上し、採用効率の改善や企業イメージのアップにもつながることが期待できます!
パート社員の雇用契約書はDottedSign(ドットサイン)で
いかがでしたか?パート社員の雇用契約書の重要性が、今回のブログで十分にわかっていただけたと思います!
そこで今後、今あるテンプレートを活用しながら、雇用契約書を電子化したいという方にオススメしたいのがKdanが提供しているDottedSign(ドットサイン)です。

DottedSign(ドットサイン)はあらゆるデバイスから、オンラインで雇用契約の締結から管理までを行うことが可能です。また、入れ替わりの激しいパート採用にも最適な「特定の宛先を指定する必要がなく、リンクを送るだけでサインができる」Public form機能も搭載しています。
さらに、DottedSign(ドットサイン)では現在利用している紙やPDFのフォーマットを直接アップロードして利用することが可能です。そのため電子サインサービスの利用経験がない方も、すぐに使い始めることができます。
DottedSign(ドットサイン)では14日間の無料トライアルも実施中です。もしこの機会に雇用契約書を電子化したい!とお考えの企業の方は、ぜひこちらからお問合せください!